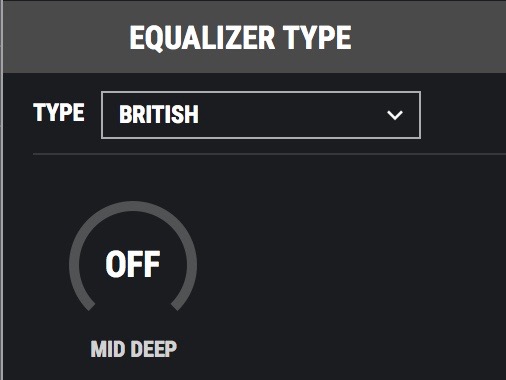すでに200シリーズの4ラインナップが発表になっておりますが、グラフィック・イコライザーの「EQ-200」と、このデジタル・ディレイ「DD-200」が先行して発売されました。例によってスペックやマニュアルは公式サイトで既に公開されています。こちらでは実際に使用したみた印象をレポートします。
スペックの確認やマニュアルのダウンロードはこちら→BOSS DD-200公式サイト
サイズ感
実際のサイズを他の現行モデルと比較してみました。
DD-500:幅 (W)170 mm奥行き (D)138 mm 高さ (H)62 mm
DD-200:幅 (W)101 mm奥行き (D)138 mm 高さ (H)63 mm
DD-7 :幅 (W)73 mm 奥行き (D)129 mm 高さ (H)59 mm
DD-500とほぼ同じ奥行きと高さ。DD-200は幅が狭くなっています。
コンパクトのDD-7と比べると、二回りほど大きいサイズに見えます。INPUT/OUTPUT端子などは側面(横)では無く、上部(奥)側にあります。
実際にボードに置いてみました。以前にDD-500を置いていた場所に設置すると200シリーズを2台並べて置くことができます。
重さは、DD-200以外のカタログ表記では電池を含んだ数値になっているようです。電池を外して実測してみると…、
・DD-200:610g(これはカタログ・スペック)
・DD-500:約900g
・DD-7 : 約400g
DD-200はかなり軽い印象です。ボードに入れるのに丁度良いサイズですね。ただ、質量の数値には誤差があると思われますので、ご参考までということでお願いします。
サウンド
サンプリング周波数96kHz、AD/DA変換32bitのスペックを誇ります。DD-200とDD-500の同じモードを選び、実際に音出しして比較してみると非常に近い音質&音色と感じました。
モード数=12個とDD-500と同数ですが、内容は少しだけ異なります。「DUCKING」や「LO-FI」、「PAD ECHO」に加え"Binson EchoRec2"のモデリング「DRUM」もダイレクトに選択可能。DD-200でも充分なバリエーションをセレクトできます。一方、DD-500からは「FILTER」と「VINTAGE DIGITAL」が省かれています。さらに、各タイプ内の細かいパラメーターも省略されていますが、DD-500のような膨大なパラメーター操作が必要無いなら、むしろDD-200の方が扱いやすいと感じるかもしれません。
ノブはディレイ・タイプをセレクトする「モード」の他、「TIME」(押すことでTempo表示切り替え)、「FEEDBACK」、「E.LEVEL」、「TONE」、「MOD DEPTH」、「PARAMETER」の7個。「PARAMETER」にはタイプに合わせて効果的なものが自動的にアサインされます。例えば、「STANDARD」を選んだときは、ディレイ音の立ち上がり具合を調整することで「SLOW ATTACK」的な効果(DD-200にはモードとしての「SLOW ATTACK」はありません)を得たり、「TONE」と組み合わせて目立ち過ぎるディレイ音をオケに馴染むようなサウンドにすることも簡単です。
操作性
マニュアルと4つのメモリーを切り替える仕様は、ツイン・ペダル・シリーズの「DD-20」などでお馴染みの仕様。「MEMORY/TAP」スイッチを長押しすることでTAP入力が可能。「TAP DIVISION」ボタンで音価を変更します。
サウンド・メイクに関する全てのパラメータはノブだけでセッティングが完了するシンプルな構成。各コントローラー(フット・スイッチ類)のアサインやキャリー・オーバー(メモリー切り替え時にディレイ音がが途切れない効果)のON/OFFなどのシステム・パラメーターは「TAP DIVISION」と「MEMORY」を同時押しすることでアクセスできます。スイッチャーを併用する場合なら、本体のエフェクトのON/OFFスイッチは不要になりますから、別の効果をアサインしても便利そう。僕なら「WARP」を常用したいところです。
「MEMORY」ボタンを長押しで設定を保存。「TAP DIVISION」ボタンの長押しで、本番などで誤動作を防ぐための「パネル・ロック」機能を起動できます。
DD-500はパソコン用のエディターが用意されていますが、DD-200にはありません。まあ、本体の操作がとても簡単なので不要でしょう。
MIDI関連
別売のちょっと特殊なケーブルを使う必要がありますが、他のモデルとのMIDI接続が可能です。外部からのプログラム・チェンジでメモリーを切り替えられるのは勿論、CC(コントロール・チェンジ)情報で各パラメーターを制御したり、テンポを同期させたりできます。USB端子はプログラム・アップデート専用とのこと。DD-500のような強力な「バージョン2」などが公開されるんでしょうか?期待したいところです。
どんな人にオススメ?
以上のことを踏まえてまとめると…、
・省スペースで多機能なディレイが欲しい。
・シンプルで簡単な操作が好み。
・サウンドの品質を重視したい。
・1台で多くのモードを切り替えて使いたい。
・ライブなどで異なるセッティングを瞬時に呼び出したい。
・DD-20の操作に慣れていて、内容をグレードアップしたい。
・スイッチャーやマルチなどでMIDI制御したい。
なんていう方にはピッタリなモデルです。今後、僕もメインで使ってみようと思ってます。
-------------------------------------------
グラフィック・イコライザーの「EQ-200」も同時発売。こちらも面白い機能が満載の、他にはちょっとないタイプの製品。もう少しいろいろ実験して、このブログでレポートするつもりです。乞うご期待!!