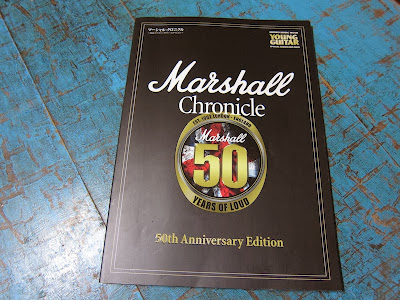8月26日(月)に山口県柳井市にある「Marshall Museum Japan」に行ってきました。今回はその魅力について詳細にレポートします。数時間滞在しただけなのですが、書きたいことが山ほどあります。最後までお付き合いください。
※「Marshall」は、ロックの歴史の中では欠かせないギターアンプを数多く製作してきたイギリスの楽器メーカーです。
※「Marshall Museum Japan」は2014年5月に山口県田布施町に移転になりました。新しいサイトは
こちら になります。
※写真をクリックすると大きな写真が見られます。更にクリックでスライドショー、写真の外側をクリックすると、このブログ画面に戻れます。お試し下さい。
アクセス方法
JR徳山駅から山陽本線で約30分。柳井駅に到着します。駅の階段を上がるともう、今回の目的地の看板が目に入ります。柳井市は岩国と徳山の間にある瀬戸内海にほど近い美しい街です。
ついに到着!
柳井駅から徒歩5分。竹谷館長を始め、スタッフの方々が温かく迎えてくれました。
2階の展示室へ。想像以上に膨大なコレクションに圧倒されます。
かの有名な解説本「The History of Marshall」の表紙になっている68年製「1959」も見えます。右はDeep Purpleのロジャー・グローバーが使用していたというベース・アンプ。
挨拶もそこそこに試奏タイムに突入!
JTM45
マーシャル史上、最初期1962年製のJTM45です。クリーン・サウンドが美しい。というか、どう言葉で表現して良いかわからないくらい、今までに経験したことのないサウンドです。単に「ぶっとい」だけじゃない。いわゆる「コンプレッション感」とも違う、抜群に弾きやすいクリーン・トーンです。(下に見えるのはこれを基にした近年のリイシュー・モデル)
1962 (Bluesbreaker)
クラプトンがギブソン・レスポール・スタンダードと組み合わせて極上のサウンドを作り上げたことで有名なコンボ・アンプです。これは正にそんな1965年製。「ブリッ」としたクランチ・サウンドが心地よい。自分のすぐ目の前で音が鳴っているような、そんな錯覚を感じます。(下の写真はミュージアムのスタッフ、EMIさんに撮影して頂きました。ありがとうございました!)
持ち込んだG-5(VGストラト)をレスポールに設定して弾いてみました。ただ、思っていたよりは歪みはそれほど強くなかったです。歪み系エフェクターと組み合わせると更によさそう。次の機会には試してみたいなぁ。
1917
PA用として製作されたという小型のアンプ・ヘッド。こちらも館長の解説を伺いながらテスト。極上のクランチ・サウンドで、時間を忘れて弾き続けてしまいます。もう、ここに住みたいです。(笑)
マーシャル・ミュージアム・ジャパンを10倍楽しむ為に
今回のレポートにもあるように、このミュージアムは、単に希少なアンプを陳列しているだけでなく、実際に弾いてみることができるんです。防音室に用意された複数のアンプ(随時入れ替えられているようですが)を爆音で試奏できます。試奏用ギターも用意されてはいるのですが、ここは是非、自分の楽器でプレイすることをオススメします。そう、ここはギターの持ち込みが可能なんですよ。普段弾き慣れた自分のギターが、個性豊かなマーシャル・アンプによってどんなサウンドを奏でるか。きっと度肝を抜かれることでしょう。
それから、ある程度マーシャルのアンプの歴史について調べてから訪問するほうが、何倍も楽しめます。シンコー・ミュージック刊の「
Marshall Chronicle 」には、ここに所蔵されているモデルが詳細な解説とともに多数掲載されています。
その防音室に移ってさらに試奏は続きます。
1959
マーシャルを代表するスタック・モデル、100Wの1973年製「1959 Super Lead」です。今までにも1959は別の場所で何度が使ったことがありますが、この個体は音がデカイ割りには耳に痛くないサウンド、さすがヴィンテージ・モデルです。モデル名は年代とは関係無く、50W仕様のものは「1987」と呼ばれます。
2203
マスター・ボリューム仕様の「2203」。「JCM800」シリーズに移行する前のモデルで78年製とのこと。今回、初めて弾きました。
「1959」系のドライブ・サウンドのまま、レベル・コントロールが可能なのが意外でした。近年(といっても10年〜20年前のモデルですが…)の「JCM900」や「JCM2000」のようなマスター・ボリューム・タイプのモデル場合は、音量によって音色がかなり変化するのに対して、音量を下げてもサウンドがあまり変わらないので、きっとライブでも使いやすいでしょう。ビデオを撮ったので見てみて下さい。(デジカメのマイクでの収音なので、実際よりもコンプ感が強めに聞こえます)
VIDEO
JTM100 P.A.
ここで館長が見慣れない貴重なモデルを持ってきて下さいました。
1965年製のPA用モデルなのだそうですが、これが何と!The Whoのピート・タウンゼンドが使用していたアンプ。まずは普通にクリーンに設定してテスト。強めに弾くと心地よいコンプレッション感と若干のクランチ感が得られます。これもビデオで確認してみてください。(これもちょっとカメラのマイク側で歪んでいます)
VIDEO
更に、リンク接続することで100Wとして動作するそうです。各ツマミでバランスを変えられますし、歪ませることもできます。
その経験が自分を変える
良い音ってなんでしょう?自分にとって心地良い音でしょう?それを見つけるために様々な楽器を試している方も多いでしょう。
一方、普通の人にとって、ヴィンテージのマーシャルの音が好きでも、それを購入して、日常的にそれを使うことはコスト的にも環境的にも難しいですよね。(そもそも買おうと思っても滅多に売ってません)
実は、「自分にとって好きな音を見つけること」、「それを経験として覚えておくこと」は、ギタリストにとって、とても重要なことなんです。もし、それがわかったなら、あとはそのイメージに自分の所有している楽器を使って近づけていけば良いのですから。勿論、必要なら別の機材を試すことだって楽しい作業になるはずです。
僕自身も家に帰ってきてから、Micro CUBE GXで演奏する時でさえ音の聞こえ方が変わり、そして設定方法やプレイそのものも変わったのではないかと感じています。「自分にとっての良い音を知る」ということが、「良い音を得る」ための最良の手段であり、このミュージアムは誰でもそんな経験を得られる貴重な場所なのではないかと思いました。
-------------------------------------------
長文、読んで頂いてありがとうございました!って、まだまだ終わりじゃないんですよ、これがっ。次回に続きます。
続きはこちら→「
続・マーシャルミュージアム・ジャパン訪問記 」